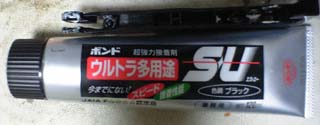|
いきなりグロっぽい画像ですが、これが外したJV-1000の錘です。平べったいのが白鍵、「ト」形をしているのが黒鍵に付いていた物です。
この赤い接着剤がJV-1000の錘落ちの原因なのですね。JP-8000に取り付けるためにはこの接着剤を取り除かなければなりません。シンナーやアルコールではこの接着剤は溶けませんでした。なので、錘をペンチで掴んでカセットコンロで熱し、接着剤が柔らかくなったところをティッシュペーパーで拭き取るという地道な作業を行いました。
|
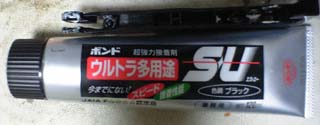 |
悪名高き(?)初期JV-1000の接着剤に代わり、新しく錘をキートップに固定するために選んだのはこのボンドSUです。金属、プラスチック共に使用でき、ゴム系なので硬化後も弾力性があります。
|
 |
JP-8000の底板を外したところです。ノブやレバーを破損させないよう、布団の上で分解をしました。キースキャン用のフラットケーブルを外します。 |
 |
鍵盤シャーシからキートップを外します。可動部分にグリスが塗られていて気持ち悪いですが我慢です。今回は押しバネを外してしまいましたが、必須では内容です。ただ無くしてしまうのが怖いので、外して小さな箱に入れておきました。 |
 |
JP-8000のキートップの中にボンドを塗り、錘をはめ込んで「ムニューッ」と押さえ込みます。
この写真は白鍵ですが、黒鍵は幅が狭くボンドを流し込むとキーガイドが当たる部分にまでボンドが付いてしまい不具合の原因になるので、ラジオペンチで錘を掴み、錘側にボンドを付け注意深くキートップの中へ埋め込むという方法で作業を行いました。
この作業を49鍵行い、硬化を待ちます。 |
 |
錘を埋め込んだキートップ、白鍵と黒鍵です。これを鍵盤シャーシに取り付け直し、鍵盤の改造は終わりです。
|
 |
鍵盤とトップパネルとの隙間が空いているのが気になるため、ピアノのように鍵盤押さえフェルトを付けることにしました。フェルトを買ってきて細く真っ直ぐに切り(けっこう難しい)、両面テープでトップパネル裏側に貼り付けます。もともとフェルトを付ける設計ではないため、基板にも貼り付いてしまっていますが、仕方がありませんね。
位置合わせは組み上がった鍵盤を仮に当ててみて行います。 |
 |
さて、全部組み立て直して斜め下から撮った写真です。こんな具合に全てのキートップに錘が付きました。
いい感じにキータッチが重くなり、弾き心地が向上しました。押しバネの力が不足してキートップが上がって来なくなるのではと心配していましたが、そういうことも無さそうです。 |
 |
上から見たところです。
ちょっと分かりづらいですが、鍵盤奥とトップパネルの間に青いフェルトが見えます。単に見栄えだけのものですが、ひょっとしたら防塵効果があるかもしれません
|