![]()
2.宝暦治水
 |
木曽川・長良川・揖斐川が氾濫して起こる水害に対して、宝暦3年(1753)12月、江戸幕府は、美濃の水害を防ぐために木曾三川の流れをよくすることを基本とした治水工事を、美濃国から遠く離れた薩摩藩(鹿児島県)に行うよう命じました。 |
(1)大槫川の洗堰
川床の高い長良川の水が、大槫川へ強く流れ込むのを防ぐため、大槫川入り口に洗堰を造りました。
洗堰は、水かさが増えてくると堰の上を水が越えて流れる仕組みになっています。
(2)油島の喰違堰(くいちがいぜき)
 |
油島付近で合流する木曽川、揖斐川の川床は1.8m程の差があるため、水かさが増えたとき木曽川の水が揖斐川に流れ込み、揖斐川沿いの村々の被害を大きくしていました。 |
(3)金森吉次郎(1864〜1930)
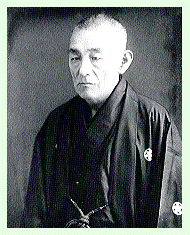 |
元治元年(1864)11月29日、大垣市魚屋町にて金四郎の次男として生まれました。 |
3.三川分流工事
(1)三川分流工事(明治改修)
 |
今から10年ほど前の明治時代になって、国は、オランダ人技師ヨハネス・デレーケを招いて三川分流工事を行いました。 |
(2)ヨハネス・デレーケ(1842〜1913)
 |
オランダのコリンスプラートに生まれ、近代化を急ぐ明治政府の招きにより、土木技師団の一人として明治6年(1873)、31歳のとき来日しました。 |