
芭蕉翁 興謝蕪村画

古池や句碑
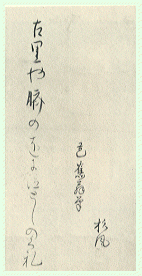
芭蕉筆跡「古里や反古」

俊乗坊重源上人像

蓑虫庵

さまざま園

孝女伊麻顕彰碑
|
貞享2年(1685)の4月、旅から帰った芭蕉は同4年の初冬までの約2年半を深川で暮した。きぴしい長旅のあとの静居は芭蕉にとって自然と人生について思索を深める沈思黙考の境涯でもあった。その静寂のなかで春には
古池や蛙飛ぴこむ水の音
の句がうまれ、秋には
名月や池をめぐりて夜もすがら
と興じ、8月には「波留濃日」等も刊行した。貞享4年も章庵で遇したが、8月には曽良を伴って常陸鹿島に仏頂禅師を訪ねた。折りからの仲秋の名月である。月見の夜は生憎の雨だったが明け方から晴れ間もみえた。
をりをりにかわらぬ空の月影も
千々のながめは雲のまにまに 和尚
月速し梢は雨を持ちながら 桃青
寺に寝てまこと顔なる月見かな
と仏頂禅師の歌に脇をついて略和した。
鹿島の旅を楽しんでから、芭蕉はさらに旅への意欲をもやし、その年の10月25日、「笈の小文」の旅を思いたった。
出発にあたって門人たちが餞別の吟を贈った。其角も関送りの句会を催すなどして、にぎにぎしく門出を祝福してくれた。芭蕉自身も「故ある人の首途するにも似たりといと物めかしく覚えられけれ」とおもい
旅人と我名よばれん初しくれ
と吟している。また「百骸九窺の中に物あり 仮りに名づけて風羅坊といふ」といい切るをど、旅人に徹した風狂心がにじみ出ている。
しかし、ここには「野ざらし」の旅のような悲愴感は薄らぎ、前々の旅で体得した風雅の誠を究めつくしたあとの拡充感がただよい、更にその深奥に迫ろうとする作家意欲は余裕すらみせている。
江戸を発ち、途中知足亭に留まり、三河の保美に杜国を訪ねたりして年末郷里に帰ったとき「代々の賢き人々も、古郷はわすれがたきものにおもはへ待るよし、我今ははじめの老も四とせ過ぎて、何事につげても昔のなつかしきままに……」と述懐し
旧里や臍の緒に泣くとしのくれ
と吟した。
想えば12才(明暦2年)の時、父と死別し、母の手ひとつで成人した芭蕉にとって、4年前(天和3年)に亡くなった母への痛哭は限りなく、「猶父母のいまそかリせばと慈愛のむかし悲しくおもふ事のみ」がこみあげる歳暮の帰省であった。
そんなこともあってか、大晦日は夜の更けるのも知らず酒を酌み明したので、二日は床に就いて寝正月を送った。ゆっくりとくつろいで新春を迎えた芭蕉はこの帰省の楽しみでもある上野の旧友と俳交を温める日々を過ごしたが、9日、上野の城下に小川風麦を訪れた。
風麦は藤堂藩伊賀付の高知役、藤堂式部組に属する藩士で、式部下屋敷の南、忍町の一郭に屋敷を構え200石を禄していた。その娘は町奉行友田角左衛門に嫁して梢風と号し、夫の良品とともに蕉門に一座する俳諧一家であった。
2月はじめ上野を発ち伊勢神官を参拝、この地で尾張の杜国と落ち合い地元の俳人たちと歌仙を興行。伊賀に帰った芭蕉は2月18日亡父の三十三回忌追善法要に参列して孝心をしめした。
その翌目杜国、宗波の二人が芭蕉を訪れた。上野の酒造家大和屋宗七に宛てた酒一升を無心する書状はこの珍客をもてなすものであろう。
2月下句、旧友宗無、宗七と連れだち上野から東5里の道程にある阿波郷富永村に俊乗坊重源が造営の新大仏寺を訪れた。
重源は治承4年(1180)12月28日平重衡の兵火で焼失した奈良東大寺の再建にあたり養和元年(1181)8月、勧進職の勅宣により、文治元年(1845)8月28日落慶の功を遂げた大仏聖人である。
もと阿波の圧は、平家の所領であったが、平家滅亡ののち没官領となり、建久元年(1190)12月12日、院庁の下文をもってさきに東大寺大仏鋳造に功労があった宋人陳和卿に知行された山田郡有丸、広瀬、阿波杣山の地である。
その後、陣和卿がこの地を東大寺浄土堂領に寄進したので重源は、新別所に念仏堂を建立して金色の弥陀三尊来迎立像並ぴに観音勢至の丈六像を安置し新大仏寺を開基したものである。
しかしこの像は江戸初期の山津波で堂宇ともども損壊し芭蕉がここを訪れたときには「伽監は破れて礎を残し、坊舎は絶えて田畑と名の替り、丈六の尊像は苔の緑に埋て、御ぐしのみ現前とおがまれさせ給ふに、−石の蓮台、獅子の座などは蓮、葎の上に堆り、双林の枯たる跡もまのあたりにこそ覚えられけれ」と愛惜し、
丈六にかげろふ高し石の上
の吟をのこした。
この長期の滞在中2月末から3月初め頃、瓢竹庵に岡本苔蘇を訪ねて、杜国とともに20日程をこの庵に遊んだ。
今も遺る「万菊丸嚊図」は、其の戯れに認めた芭蕉の機智によるもので滑稽な芭蕉の一面をのぞかせています。
瓢竹庵のすぐ西隣に蓑虫庵がある。3月4日、新庵を結んだばかりの庵に土芳の庵日記には
11日芭蕉翁を宿する夜
おもしろう松かさ燃えよ朧月 土芳
の句がある。その後、面壁の画讃に「みの虫の音を聞きにこよ草の庵」の句を認めた一軸を土芳に贈ったことから、蓑虫庵と号した。
土芳は芭蕉の生涯を通じてもっとも誠実な門人として、其の教えを守り蕉門伊賀連衆の中核的役割を果たした。
この帰省中芭蕉は旧主藤堂新七郎家の花見の宴に招かれた。芭焦が退身した頃には幼児であった蝉吟の遺児臭長も立派に成人して23才の若大将となっていた。芭蕉との面識もない間柄であるが母の小鍋(蝉吟室)から旧臣当時の物語をきいたであろうし、自分も探丸と号して俳諧を嗜む父祖ゆすりの文学青年であってみれば、いま江戸で評判の俳諧師芭蕉を賓客として迎えることは大いなる歓びであった。
この時芭蕉は
さまざまの事おもひ出す桜かな
の句をもって扶拶し、探丸は、これをうけて
春の日はやくふでに暮行
と脇して歓待した。
清記された懐紙には「探丸子のきみ別墅の花みもよほさせ給ひけるにむかしのあともさながらにて」と前詞をつづり、こもごもに去来する懐旧の情をあらわして、今更ながら主従のきずなをかみしめている。
この劇的な場となった新七郎家の下屋敷は上野城第三郭の要塞の地にあって四周の眺望は季節の変化に富む明媚な位置を占めている。
その景趣によって中国瀟湘八景になぞらえ八景亭と名づけられていたが、芭蕉との再会を記念に「さまざま園」とよばれるようになった。
花のさかりをふる里で過ごした芭蕉は「弥生なかば過るほど そぞろに浮立つ心の花の われを導く枝折となりて」吉野の花見に出掛けた。その出発ちに苦蘇への滞在の謝辞をこめて
このほどを花に礼いふ別れかな
の句をのこし、杜国を伴ない19日に上野をたった。この道程は「道のほど百三十里此川舟十三里駕籠四十里歩行路七十七里雨にあふ事十四日」の長旅となった。
伊賀を出て兼好の旧跡を種生村に訪れ、初瀬、葛城山、三輪、多武峯、臍峠、龍門をめぐり、吉野山に入った。ここでは西行ゆかりの旧庵苔清水、西河、蜻鳩の滝に足を運ぴ軍書に悲しといわれる吉野哀史を心にとどめながらも、桜の見事ざに句をつくらず三日を過して高野に赴いた。
父母のしきりに恋し堆子の声
の句は、齢すでに45才を迎えた芭蕉の「久不想見長母想忘」という情感のこもった吟である。
高野を下って三月末和歌浦、紀三井寺にも参詣。ここから奈臭にひき返して、上野からきた猿雖、卓袋、梅軒と再会した。
その後も芭蕉は精力的に古跡を巡遊して唐招提寺では鑑真和上の像を拝し、丹波、八木を経て12日には竹内村に孝女伊麻を訪れた。
芭蕉は伊麻の孝心を非常に尊敬し、のち猿雖から東麗庵、西麓庵の扁額に揮毫を所望ざれた析に、庵額の揮毫者として伊麻を推挙したほどであった。更に西に竹内峠を越え、河内に入って誉田八幡に泊り、大坂に着いた。
大坂には伊賀の旧友保川一笑がいた。伊賀を出て久しくこの地で紙屋を営む富有な町人であった。ここに草鞋を脱いだ芭蕉と杜国は一笑を交えて三吟二十四句をのこし、
杜若語るも旅のひとつ哉
を句吟した。
大坂の地に6日間滞在ののち、芭蕉と杜国は船で須磨、明石の名所旧跡を一巡して、その夜は須磨に泊り、翌日京へ上った。
ここから直ぐ江戸に帰るべくして大津から岐阜、鳴海を経て名古屋に着いたのは八月のことであった。「十八楼の記」はその途路、岐阜の賀島鴎歩の水楼に遊んだときの稿で
このあたり目に見るものは皆涼し
と打ち興じた。
|






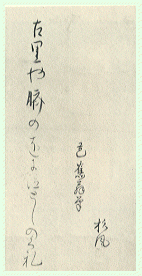




芭蕉筆跡 更科紀行草稿