俳聖 芭蕉翁(4)
俳聖 芭蕉翁シリーズ
奥の細道(2)
【石の巻】 5月10日(新暦6月26日)
十二日、平和泉と心ざし、あねはの松・緒だえの橋など聞伝て、人跡稀に雉兎蒭蕘の往かふ道そことも
わかず、終に路ふみたがえて、石の巻といふ湊に出。
「こがね花咲」とよみて奉たる金花山、海上に見わたし、数百の廻船入江につどひ、人家地をあらそひて、
竈の煙立ちつゞけたり。
思ひかけず斯る所にもきたれる哉と、宿からんとすれど、更に宿かす人なし。
漸まどしき小家に一夜をあかして、明れば叉しらぬ道まよひ行。
袖のわたり・尾ぶちの牧・まのゝ萱はらなどよそめにみて、遥なる堤を行。
心細き長沼にそふて、戸伊摩と伝所に一宿して、平泉に到る。
其間廿余里ほどゝおぼゆ。
|
【平泉】 5月12日(新暦6月28日) 三代の栄耀一睡の中にして、大門の跡は一里こなたに有。 |
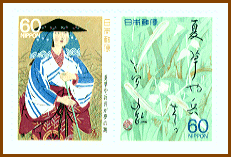 |
【尿前の関】 5月14日(新暦6月30日)南部道遥にみやりて、岩手の里に泊る。 |
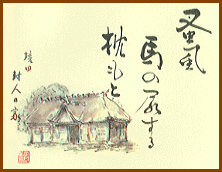 |
【尾花沢】 5月17日〜(新暦7月3日〜)尾花沢を清風と伝者を尋ぬ。 |
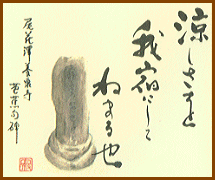 |
【立石寺】 5月27日(新暦7月13日)
山形領に立石寺と伝山寺あり。
慈覚大師の開基にして、殊清閑の地也。一見すべきよし、人々のすゝむるに依て、尾花沢よりとつて返し、其間七里ばかり也。
日いまだ暮ず。麓の坊に宿かり置て、山上の堂にのぼる。
岩に巌を重て山とし、松柏年旧、土石老て苔滑に、岩上の院々扉を閉て、物の音きこえず。
岸をめぐり、岩を這て、仏閣を拝し、佳景寂寞として心すみ行のみおぼゆ。
閑さや岩にしみ入蝉の声
【最上川】 5月28日〜(新暦7月14日〜)最上川のらんと、大石田と伝所に日和を待。 |
 |
【羽黒】 6月3日(新暦7月19日)六月三日、羽黒山に登る。 |
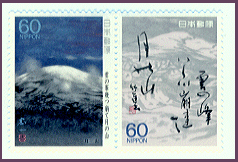 |
【酒田】 6月13日(新暦7月29日)
羽黒を立て、鶴が岡の城下、長山氏重行と伝物のふの家にむかへられて、俳諧一巻有。
佐吉も共に送りぬ。
川舟に乗りて、酒田の湊に下る。
淵庵不玉と伝医師の許を宿とす。
あつみ山や吹浦かけて夕すゞみ
暑き日を海にいれたり最上川
【象潟】 6月18日〜(新暦8月3日〜)江山水陸の風光数を尽して、今象潟に方寸を責。 |
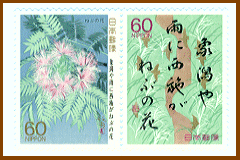 |
【越後路】 6月26日(新暦8月11日)酒田の余波日を重て、北陸道の雲に望。 |
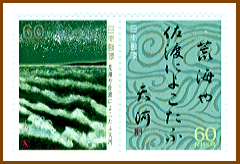 |
【一振】 7月12日(新暦8月26日)
今日は親しらず・子しらず・犬もどり・駒返しなど伝北国一の難所を越て、つかれ侍れば、枕引よせて寐たるに、一間隔て面の方に、若き女の声二人計ときこゆ。
年老たるおのこの声も交て物語をするをきけば、越後の国新潟と伝所の遊女成し。
伊勢参宮するとて、此関までおのこの送りて、あすは古郷にかへす文したゝめて、はかなき言伝などしやる也。
白浪よする汀に身をはふらかし、あまこのこの世をあさましう下りて、定めなき契、日々の業因、いかにつたなしと、物伝をきくきく寝入て、あした旅立に、我々にむかひて、「行衛しらぬ旅路のうさ、あまり覚束なう悲しく侍れば、見えがくれにも御跡をしたひ侍ん。衣の上の御情に大慈のめぐみをたれて結縁せさせ給へ」と、泪を落す。
不便の事には侍れども、「我々は所々にてとゞまる方おほし。只人の行にまかせて行べし。神明の加護、かならず恙なかるべし」と、伝捨て出つゝ、哀さしばらくやまざりけらし。
一家に遊女もねたり萩と月
曾良にかたれば、書とゞめ侍る。
【那古の浦】 7月14日(新暦8月28日)くろべ四十八が瀬とかや、数しらぬ川をわたりて、那古と伝浦に出。 |
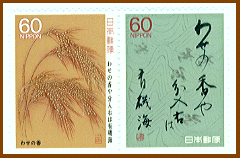 |
【金沢】 7月15日(新暦8月29日)卯の花山・くりからが谷をこえて、金沢は七月中の五日也。 |
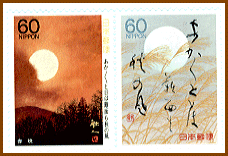 |
【小松】 7月24日(新暦9月7日)
小松と伝所にて
しほらしき名や小松吹萩すゝき
此所、太田の神社に詣。
実盛が甲・錦の切あり。
往昔、源氏に属せし時、義朝公より給はらせ給とかや。
げにも平士のものにあらず。
目庇より吹返しまで、菊から草のほりもの金をちりばめ、竜頭に鍬形打たり。
実盛討死の後、木曽義仲願状にそへて、此社にこめらし侍よし、樋口の次郎が使せし事共、
まのあたり縁起にみえたり。
なざんやな甲の下のきりぎりす
|
【那谷】 山中の温泉に行ほど、白根が獄跡にみなしてあゆむ。 |
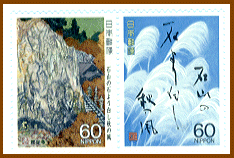 |
【山中】 7月27日(新暦9月10日)
温泉に浴す。
其功有明に次と伝。
山中や菊はたおらぬ湯の匂
あるじとする物は、久米之助とて、いまだ小童也。
かれが父俳諧を好み、洛の貞室、若輩のむかし、爰に来りし比、風雅に辱しめられて、洛に帰て貞徳の門人となって世にしらる。
功名の後、此一村判詞の料を請ずと伝。
今更むかし語とはなりぬ。
曾良は腹を病て、伊勢の国長島と伝所にゆかりあれば、先立て行に、
行き行きてたふれ伏とも萩の原 曾良
と書置たり。
行ものゝ悲しみ、残ものゝうらみ、潟鳧のわかれて雲にまよふがごとし。
予も又、
今日よりや書付消さん笠の露
【全昌寺・汐越の松】 8月上旬大聖寺の城外、全昌寺といふ寺にとまる。 |
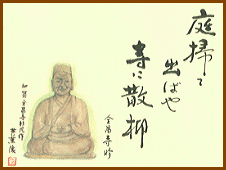 |
【天竜寺・永平寺】 8月上・下旬
丸岡天竜寺の長老、古き因あれば尋ぬ。
又、金沢の北枝といふもの、かりそめに見送りて此処までしたひ来る。
所々の風景過さず思ひつゞけて、折節あはれなる作意など聞ゆ。
今既別に望みて、
物書て扇引さく余波哉
五十丁山に入て、永平寺を礼す。道元禅師の御寺也。邦機千里を避て、かゝる山陰に跡を
のこし給ふも、貴きゆへ有とかや。
【等栽】 8月12日(新暦9月25日)
福井は三里計なれば、夕飯したゝめてでるに、たそかれの路たどたどし。
爰に等栽と伝古き隠士有。
いずれの年にか、江戸に来りて予を尋。
遥十とせ余り也。
いかに老さらぼひて有にや、将死けるにやと人に尋侍れば、いまだ存命して、そこそこと教ゆ。
市中ひそかに引入て、あやしの小家に、夕貌・へちまのはえかゝりて、鶏頭・はゝ木々に戸ぼそをかくす。
さては、此うちにこそと門を扣ば、侘しげなる女の出て、「いづくよりわたり給ふ道心の御坊にや。あるじは此あたり何がしと伝ものゝ方に行ぬ。もし用あらば尋給へ」といふ。
かれが妻なるべしとしらる。
むかし物がたりにこそ、かゝる風情は侍れと、やがて尋あひて、その家に二夜とまりて、名月はつるがのみなとにとたび立。
等栽も共に送らんと、裾おかしうからげて、路の枝折とうかれ立。
|
【敦賀】 8月14日(新暦9月27日) 漸白根が獄かくれて、比那が嵩あらはる。 |
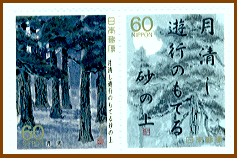 |
【種の浜】 8月16日(新暦9月29日)十六日、空晴たれば、ますほの小貝ひろはんと、種の浜に舟を走す。海上七里あり。 |
 |
【大垣】 8月21日〜9月6日(新暦10月4日〜18日)露通も此のみなとまで出むかひて、みのヽ国へと伴ふ。 |
 |