三重県の伊賀上野にある芭蕉翁記念館へ行って来ました。
芭蕉翁顕彰会発行の「俳聖芭蕉翁」より抜粋しています。
俳聖 芭蕉翁シリーズ
俳聖 芭 蕉 翁
三重県の伊賀上野にある芭蕉翁記念館へ行って来ました。
芭蕉翁顕彰会発行の「俳聖芭蕉翁」より抜粋しています。
俳聖 芭蕉翁シリーズ ![]()
![]()
![]()
![]()
生い立ち
 |
芭蕉は寛永21年(1644)甲申の年に生まれました。 |
伊賀の風土
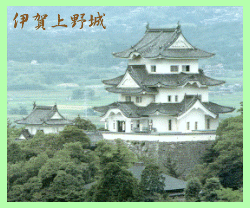   |
伊賀の国は地質学上、古琵琶湖層群とよばれる湖盆の国原で、四周を山に囲まれ伊賀一国からなっている。盆地の中央やや北寄りに浸蝕からとり残された上野台地がある。 |
青年期
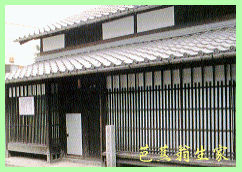 |
芭蕉は青年期を伊賀上野ですごし幼名を金作と称した。 |
蝉吟の死
寛文5年11月13日、蝉吟は季吟の脇句を得て、貞徳十三回忌追善百韻を興行した。一座の連衆は蝉吟を中心に上野町人窪田正好、保川一笑、松木一以らであり、芭蕉もまた宗房の名でこれに加わった。
ところが、翌年4月25日、蝉吟が僅か25才を一期として、花のこぼれちるなかになくなった。この主君の死は23才の多感な青年芭蕉の生涯に一転機を与える重大な年となった。
大きな衝撃をうけた芭蕉は悲しみに沈むなかで、去就に悩みぬいたすえで退身を決断したにちがいない。これには多くの物語が伝えられている。
貝おほひ
  |
その後、6年間の空自をのこして、芭蕉の存在が鮮明になるのは、彼の処女作、三十番俳諧合『貝おほひ』の出現である。 |
故郷を出ず
 東京都深川の芭蕉庵跡 |
「貝おほひ」を上野の産土神に奉納した芭蕉は、この年の春、江戸に下ったものと考えられる。 |
江戸の芭蕉
江戸に下った芭蕉の足取りは、伊賀在郷の時代に比べると、かなり記録や文献に恵まれるようになる。
そのことは、とりもなおさず芭蕉の存在が俳壇史の上に重要な位置を占めるようになったことを物語るものであるが、芭蕉自身にとって苦闘の時代でもあった。
あたかもその時、俳諧史は展開期に際会していた。大坂天満宮の連歌宗匠西山宗因も江戸に下った。
江戸俳壇にも宗因の影響がおよぴ、延宝3年(1675)5月、深川大徳院では宗因を歓迎する百韻が興行された。この百韻には宗房を桃青と改めた芭蕉も、幽山、信章などとともに一座に加わった。
その翌年、山日素堂と二人して興行した天満宮奉納二首韻で芭蕉は、宗因流の自由な放笑性に傾倒する輝連な句をもって素堂に唱和している。
ついで同5年、俳諧大名として知られる内藤風虎の催した「六百番俳諧発句合」に二十句を出句し、いよいよ芭蕉は江戸在来の俳壇を圧するばかりの出色した才能をここに現したのである。
その評判が江戸の地にひろがるにつれ、田態のマンネリズムに退屈していた俳人達は芭蕉を慕って集った。芭蕉にとって、ついに生涯のはかりごととなった宗臣9つ署立机の夢はようやく実を結ぴ、その披露の万句興行も行われた形跡がある、次いで翌6年には歳且帳も出したらしい。
しかし、生計のほうはあまり楽ではなかったらしく、芭蕉が江戸に出て神田水道の工事に従事していたというのは、この頃から延宝8年(1680)に至る約4ヶ年間のことと思われる。
一方「将軍さまのお膝元」といわれる政治都市江戸での生存競争は、田舎者の芭蕉にとって殊のほかきぴしいものであった。
そうした世情にもかかわらず、延宝8年(1680)4月、芭蕉が37才のときに刊行した「桃青門弟独吟二十歌仙」は、彼の宗匠としての確固たる地位を示すもので、杉風、ト尺、厳衆、一山、緑糸子、僊松、ト宅、自豚、杉化、木鶏、嵐蘭、楊水之、嵐亭(嵐雪)、螺舎(其角)、巌翁、嵐窓、嵐竹、北*、岡松、吟桃の各独吟二十歌仙一巻をおさめ、追加に館子の独吟歌仙一巻を添えたものである。
驚くべきことに、僅か数ヶ年の間に、芭蕉を中心にこれだけの俊才があつまり、俳壇の最先端に位置したのであった。
ついで、同じ 年の秋には其角の自句合「田舎句合」と杉風の自句合「常盤屋句合」に師匠の芭蕉が判詞を添えた姉妹編が続刊された。
このように芭蕉一門が活気を帯ぴてくると、「江戸の流れ者」として、とかく白眼視されてきた芭蕉であったが、つぎつざと世間を白己の世界へ誘いこむ新規な活躍ぶりをみて、人々はもはや芭蕉を軽視することができず江戸を代表する六名の宗匠の一人として、その存在を認めずにはいられなくなった。
荘子礼讃
そうして、「生き馬の目を抜く」とさえいわれる都会生活での人間関係はきぴしく、芭蕉の名声が高まれば高まるだけ、利害得失、名誉栄達を競う複雑な生存競争がうずまき、芭蕉の心を悩すことが多くなった。
やっと思い望む宗匠の座を獲得したとはいえ煩悶(はんもん)の情は尽きず、さまざまな懐疑を抱くようになった。その懐疑な芭蕉の心をめばえさせたのは、とりもなおさず古代中国の聖哲「荘子」の人生哲学であった。荘子は宇宙の根本原理から人間と人生の理想的な存在を説いている。
芭蕉もまた、この荘子に心を傾け「天に従うを道と謂う、道に従うを自然と講う矣」と自註する自然観照の念を至上としていたので、世間の人間葛藤や毀誉褒麗(きよほうへん)に嫌厭し宗匠稼業を捨て、深川の草庵に隠棲(いんせい)した。延宝8年(1680)冬のこと、芭蕉37才の時であった。
この草庵は杉風の生洲(いけす)屋敷だったといわれ、小名木川が隅田川に注ぐ川口に近い場所であった。芦荻のおい茂る愛閑の地は社甫(中国の詩人)の「門ニハ泊ス東呉万里ノ船」と詠んだ詩情に似ることから、名づけて泊船堂といい、傾く月光に風雅をおもい、詩聖のこころを慕いつづける生活を楽しんだ。
天和元年(1681)芭蕉の草庵に門人の李下が芭蕉一株を贈った。その生青がよくいつしか庵の名物になったので「芭蕉庵」とよばれていた。芭蕉自らも芭蕉庵桃青と号し、天和2年頃から正式に芭蕉の号を用いるようになった。
しかし、芭蕉はこの庵住で閑住するつもりはなかった。社甫、李自、蘇東波などの世俗を去って高雅な詩境に人生を送った文人達を慕い、権勢覇争をのがれて草庵に隠れた西行、宗祗らの中世詩人たちを、理想像にえがきながら、言葉の滑稽をもてあそんで、駄洒落(だじゃれ)の遊戯に生命を削る自分の姿がいかにむなしく無意味なものであるかとさえ疑いをもち草庵の近くの臨川寺に寄寓(きぐう)する仏頂禅師に就いて禅を学んだ。
そして得た禅的観照が彼の俳諧に新たな深みを加えるとともに「無能無芸にして只この一筋につながる」自己へのめざめを体得するに至った。
この頃芭蕉は談林の形式から脱皮しようとして、新しい風体を模索していた。その展開の軸をなすものは漢詩文調への指向であり、一種の新しいリズムを与えた。
枯枝に鳥とまりたるや秋の暮
雪の朝独り干鮭を噛得タリ
佗テすめ月佗斎がなら茶歌
氷苦く偃鼠が咽をうるはせり
などの句は、緊追したリズムのもつ悲愴感と、現実の俗から脱した高雅な詩境に自らの生活を観ずるものとなり、独得の詩趣をただよわせるものとなった。
とりわけ天和3年に出た其角の「虚栗(みなしぐり)」によせた芭蕉の跋文(あとがき)である。つまり、「李、杜が心酒を嘗て寒山が法粥を啜る・・・・・」にはじまる一節は漢詩的、禅的風韻と、当時の俳諧観をしめすこの時代の代表作品ということができる。