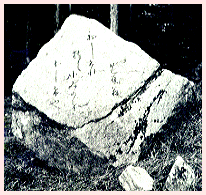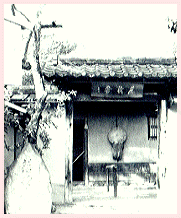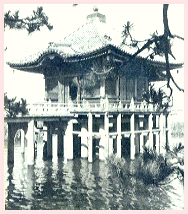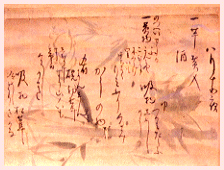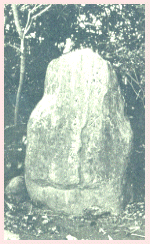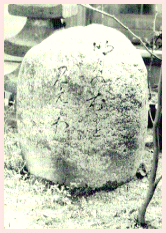中村不析画
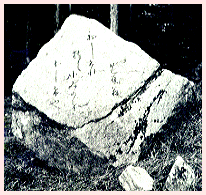
猿 蓑 塚(大山田村伊賀街道脇)

桜麻塚(須知荒木神社)
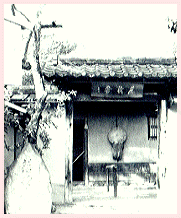
去来の落柿舎
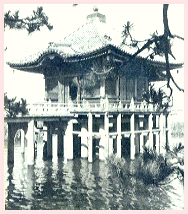
堅田の浮御堂
|
「おくのほそ道」の旅を終えた芭蕉は伊勢の長島から久居に入り、数日後に江戸からきた李下を伴って郷里上野に第六回めの帰省をした。その途路、伊賀街道を西に長野越えに進み、山中で
初しくれ猿も小蓑をほしげ也
とよんで上野に入った。 この旬は『猿蓑』の巻頭旬に掲げられて冬の季題に入っているが、その作意には晩秋の気配がみなぎる名句である。
芭蕉の旅に終始随行した曽良は八日にひと足さき上野に着き、伊勢でひとまず別れた路通も伊賀に来たので、芭蕉の兄半左衛門方で芭蕉の帰着するのを待っていた。
郷里に帰った芭蕉は門人、知已の歓待をうけ、風麦、良品、梢風、半残、梅額、木白、配力、園風、一入、平仲らの句会に招かれ、それぞれの句吟をのこしたが十一月末、奈良の祭礼見物におもむいた。
初雪やいつ大仏の柱立
は、大仏の再興をよろこぶ吟である。芭蕉はさらに湖南、京都、大津、膳所におもむき、この地で越年、近江の蕉門と親交をわかち、
少将のあまの咄や志賀の雪 はせを
あなたは真砂麦はこがらし 智 月
という句文をのこしている。 あけて元禄三年(1690)正月三日、郷里上野に停った芭蕉は三月頃まで滞在した。その間二月六日西島百歳の邸で俳席が催された。百歳、乍木、村鼓、式之、梅額、一桐、槐市、呉雪らも一座して歌仙を巻いた。ついで、三月二日、小川風麦亭において、
木のもとに汁も瞼も桜かな
を発句とした歌仙が與行され、風麦、良品、土芳、雷洞、半残、三園、木白らが加わった。これらはすべて蕉門伊賀連衆に属した上野の俳士であるがなかには所伝未詳の人物もいる。この滞在中、芭蕉は伊賀の名所古跡を尋ねる意向をしめしたので三月十一日、その探訪を兼ねて木白が荒木村の白髭神社(周知荒木社)で連句を興行した。その吟に
畠打音やあらしのさくら麻 はせを
の句がある。また、花垣の里に名木八重桜を観にでかけた。この里は「古今著聞集」などの古書にあらわれる奈良八重桜の故事で知られた処、この所伝に拠って芭蕉は
一里は皆花守の子孫かや
と詠んだ。さらに藤堂橋木邸に遊び
土手の松花やこぷかき殿作り
の句をのこした。橋木は上野城内二之丸に屋敷をもつ伊賀付の高知役で、千五百石を禄して藤堂修理長定と称したが、宝永七年(1707)三十七才で没したことから、芭蕉との対面は橋木十七才、芭蕉四十七才の頃であった。
この滞在中芭蕉にとってひとつの悲報がもたらされた。吉野、高野山の旅に万菊丸と偽称してつれだった愛弟子杜国が三月二十日、三河国美保の隠宅で死去したことである。杜国は蕉風初期の門人のなかでも力量のある俳人であった。芭蕉の悲嘆をきわめ「夢に杜国が事をいひ出して沸泣して覚む」とあるほど落胆し哀惜する芭蕉であった。
芭蕉は三月末に近江の膳所に酒堂を訪れ寄寓した。酒堂は医を職とする名望家で初号を珍碩、珍夕といい、酒堂は酒落堂によるものである。俳諸を尚白に学んだが元禄二年頃、芭蕉を師として蕉門に入った。
その後芭蕉は四月六日から七月二十三日にかけて石山寺の西北にあたる国分山の幻住庵に入った。この草庵は菅沼曲水の伯父菅沼定知の庵であるが定知が死去してのち、久しく荒廃にまかせる空居であったが曲水のはからいで修復し芭蕉を迎えいれたものであった
「石山の奥岩間の後ろに山あり国分山といふ!」
にはじまる『幻住庵の記』は『おくのほそ道』『嵯峨日記』とともに芭蕉俳文の名著にふさわしく先たのむ椎の木もあり夏木立の句とともに漂泊安住の、心境を伝えるものである。秋だって幻住庵を出た芭蕉は、大津の無名庵に入ったかなここで八月十五夜の名月を賞で
名月や兄たち並ぶ堂の稼
名月や海にむかへは七小町
明月や座にうっくしき顔もなし
とうち興じて、九月には堅田の本福寺に千那を尋ねたが帰って風邪で寝込んでしまった。この呻吟を堅田の落雁にも例えて
病雁の夜さむに落ちて旅寝かな
と悲愁にくれる心情を吐露している。九月二十七日芭蕉は無名庵から京に上ったがすぐ引返し翌日伊賀に帰った。その道すがら、寒村の抒情にひかれて
しぐるるや田のあらかぶの黒むほど
の句を残した。帰省した芭蕉は十月氷固亭に招かれた。氷固は後の非群であり上野町の商家である。
きりきりすわすれ音になく火燵かな
の立句で歌仙一折を興行したと伝えられる。暫くして芭蕉は再び京に上り、大津で越年した。乙州の新宅で春を待ち
人に家をかわせて我はとし忘れ
と酒落こみ、その健在振りをしめしている。明けて元禄四年四十八才の春を迎えた芭蕉は正月、乙州が江戸に赴く送別の句会において
梅若菜まりこの宿のとろろ汁
の句を餞別とした。その頃、
大津絵の筆のはじめや何仏
住みつかぬ旅のこころや置火燵
の句を披露して大津を去った。その停路、伊賀の山中で
山里は万才おそし梅の花
の吟をえて、伊賀に帰着ののち、藤堂橋木亭の句会において、この句を披露した、二月には奈良の薪能を見物するために出かけ、再び伊賀に帰るあわただしい日を過したが三月二十三日上野札ノ辻で両替業を営む大坂屋万乎の別邸に観桜句会があった。
芭蕉は
年々や桜を肥やす花の塵
の自句を発句として歌仙一折を巻いた。ただしこの歌仙は伝存せず、同席した連衆の名さえもわかっていない。
出郷の月日は明らかではないが三たび伊賀を出た芭蕉は京から嵯峨にむかい四月十八日去来の落柿舎に入った。落柿舎は門人の去来の別邸。窪田猿錐肖像清閑の地は芭蕉のあわただしい旅から旅へのあけくれに一抹の楽しみを与えてくれた。
その起居のさまをつぶさに日記風にかいたのが「嵯峨日記」として知られる庵住のさまである。
そのときの草稿と推定される「落柿舎の記」もまた味わい深い愛閑の記である。
時折り門人達が訪れてきた。凡兆妻の羽紅尼、去来、千那、史邦、丈草、李由、曽良も芭蕉の寂び住いを訪れ、団欒して過すこともあったが、人々が帰ってしまうとまたもとの静寂に戻った。孤独に馴れた芭蕉にとっても、やはり独居は淋しいものである。
眠れぬまま
憂き我をさびしがらせよ閑古鳥
と詠んでいる。その間京都、湖南の地を往返し、凡兆宅、無名庵などにも滞在することもあった。ちょうど七月には凡兆、去来が共編する「猿蓑」が刊行された。この集は蕉風俳諸の最高峰を示すものであり、伝統の芸道が伝承してきた「さび」「しをり」「ほそみ」などの理念を俳講という形式のなかに定着させ、連句の「にほひ」「うつり」「ひびき」に受け継がれた。
今年の観月には待宵を楚江亭ですごし、名月の夜は無名庵の木曽塚で月見の句会を催し、いざよい月を堅田の舟上で賞した。そして九月二十八日義仲寺を発ち江戸に向って旅だった。門人支考、桃隣が同行した。
|