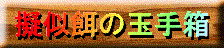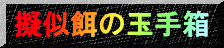|
ミノー・シャッド |
| ||
|
トップウォーター |
| ||
|
豪州ルアー |
|||
|
気になるルアー |
| ||
|
お助けルアー |
|
|
 ハートの数はオーストラリア遠征必携度合い)
ハートの数はオーストラリア遠征必携度合い) サンドバイパー Predatek
サンドバイパー Predatek 
リップ を含めた全長は15cm、重さは28g。ボディ後半が極端に絞り込まれており、一目見れば強く脳裏に刻み込まれる個性的なスタイルを持つルアー。カン高いラトル入りの太軸3本フック仕様、メインターゲットはもちろんバラマンディだ。NSW州にあるこのメーカーPredatek社が"ロックンロールアクション"と呼ぶ動きがウリ。サンドバイパーは定評のあるバイパーのシャローエリア攻略モデルで、グリフォンのような矢じり型のリップがボディにしっかりと装着されている。
トローリングで使うのがメインだがキャスティングでも使える。サンドバイパーが最大で4m、ハイパーバイパーは9m近く潜るが、このモデルは1mが設定されている。グッと絞り込まれた特徴あるボディ形状がフッキング率向上に役立っており、2番目、3番目のフックが口の中にガッチリと掛かる仕組みとなっている。いかにもオーストラリアのルアーって感じのカラーが色々と揃っているので、カタログのカラーチャートを眺めるだけでも楽しいのだ。
 ビルズバグ Bill's Bugs
ビルズバグ Bill's Bugs 
透明なプラスチックのペラが2つ付いているトップウォータールアー。日本では"スウィッシャー"だが、現地ではペラが付いているルアーを総称してFizzerと呼んでいる。シャ〜シャ〜、ジャ〜ジャ〜と音を立てながら泡立てるヤツなので、こう呼ばれるのだろう。トップに躍り出る魚は大きく活性も高いので、一見、大雑把な感じを受けるが作りはいたって頑丈。ネジった太いワイヤーがボディを貫通しており、太軸のリングとド太いフックが装着されている。
ペラの回転は・・・見た目どおり、悪い(笑)。多分、使っている内に軸穴が削られて広がるので回転は良くなるだろうが、それまで使い続けられるかは疑問が残るところ。因みに価格は15cmのMiceBug(写真上段)がA$11.95、20cmのRatBug(写真下段)がA$12.99-13.95。昔、購入したのはウッド製だったが、後年購入した物はボディにメーカー名がクッキリと刻まれておりプラスチック製ではないかと思われる。
 LITTLE LUCIFFER
LITTLE LUCIFFER 
リーディーズルアー(Reidy's LURES)のカン高い音質のラトル入りで2.5m潜るプラスチック製のクランクベイト リトルルシファー。全長6.5cm、重さは11gの小型のルアーなのだが豪州の猛魚と対峙することから太軸フックとリングがしっかり装着されている。バラマンディだけでなく、マングローブジャック、バス、ブリームやサラトガなど魚種を問わず実績があるルアーとして知られている。
豪州のルアーでリップにラインアイがある物は、短い太軸ワイヤーをΩ型に曲げてスプリットリングで抜けないように支えているスタイルが主流。リトルルシファーもこのスタイルを継承している。日本のルアーにはないラインアイの構造なのでなんとなく心配なのだが、かなり丈夫で滅多に壊れないようだ。
 バラプロ・ミニ C-Lures
バラプロ・ミニ C-Lures 
オーストラリア・クイーンズランド州のBY DY & CJ FRYが送り出している御当地ルアーのCルアー。田舎のガソリンスタンドでもCルアーは売っているので、クイーンズランド州では誰もが知っている。かつて太っ腹プレゼント企画で提供したミノータイプのルアーや、ここに紹介したクラングベイト、シャド系ルアーもある。同社のルアーはウッド製のハンドクラフトで、その浮力を活かしキビキビとした泳ぎがウリ。バラプロ・ミニはリップが抜け落ちないようにボディの下部からピンを打ち込むなど心遣いが嬉しい。泳ぎはタンクテスト済で価格はA$13.75。日本のバス釣りでも活躍しそうなルアーであり、色使いもオーストラリアっぽい。コイツで釣れば注目度は高いだろう。
 キラルアーバラベイト、バスベイト Killalure
キラルアーバラベイト、バスベイト Killalure 
PISCATORIAL ENTERPRISES社のバラベイトとバスベイト。随分昔に駿東郡長泉町のプロショップ カサハラでワゴンセールで購入したルアーだ。今ではこの製造元はないようなのだが、同名の有名ルアーがBasser Millyard社から販売されている。吸収合併されたのかは定かではなく、ルアーの名前は残っているが同スタイルのルアーを見つけることは出来ない。
豪州の古い本を見ると、同じような形のルアーを多々見ることが出来るので一時代を築いたルアーだろう。詳細を知っている人がいたら、是非教えて欲しい。なお、バラベイトはフラットサイドで幅広リップを持つ形状。トウィッチをした際の移動距離は短く、ヒラを打ちやすく作ってある。バラマンディの攻略に主眼を置いたルアーなのだ。
 ナイトウォーカー HALCO
ナイトウォーカー HALCO 
ご存知、ハルコ社のサーフェイス・クローラー。日本国内でも一時期販売されたため、ショップの店頭で目にした事がある人もいるだろう。このナイトウォーカーは、軽い音がするラトル入りでジッターバグを連想するカップが頭部に付いているノイジー系ルアーだ。夜釣り向けとあってカップは夜光のプラスチック製なのである。マスタッド製の食い込みが良いフックが装備されているが、豪州製ルアーにしては珍しく細軸。ロッドを構える角度を高くしたり、低くすることでアクションが変わるので、状況に合った動きとポコポコ・サウンドを見つけるのが釣果を伸ばすコツだ。ワニが生息する場所では夜釣りはご法度なので、やはり日本の野池でバスを釣るのがよろしいのではないかと思う。
 グレムリン JAYSEA LURES
グレムリン JAYSEA LURES 
「ジタバグのオーストラリア版」と言い切られては、グレムリンの愛好者が黙っていられない。セミや水鳥が羽を広げたような格好で水面を軽やかにパシャパシャと動く姿は、ジッターバグとはまたひとつ趣が異なって可愛らしいのだ。オーストラリアンバスやブリーム、コッドをターゲットとして作られたルアー。ポコポコとストレートリトリーブをするだけではなく、オーバーハング下でちょこちょこと動かし、水面に落ちたセミのように演出するのも効く。
なお、このルアーは案外、華奢なフックが装着されているので太軸フックに交換してやると、格段に水絡みがアップ。日本でのバスの夜釣りで力を発揮する。羽が両サイドに張り出しているボディ形状であるためフッキングミスをする事もあるが、フックサイズを大きくしてカバーすると良いだろう。
 パトリオット65 JAYSEA LURES
パトリオット65 JAYSEA LURES 
グレムリンを作っている会社と同じJAYSEA LURESのルアー。価格はA$11.99。サイズやリップの大きさにバリエーションがあり、当モデルは4m程度潜る設定になっている。バラマンディの釣りはトローリングが主流なのだが、リップの長いクランクベイトやシャッドは、キャスティングでストラクチャー周りをタイトに攻める釣りに向いている。大きなリップと高い浮力で根掛りを回避できるのだ。日本のルアーはどれも浮力が足りず、このような釣りで使えるルアーは極めて限られているのだが豪州のルアーはその点で非常に優れている。
なお、このパトリオットのラインアイは大きなスナップが装着されているだけなので、直接これにラインを結ぶことになる。ルアー交換が激しい釣りにおいてはチョット面倒。ルアー交換するたびに、ショックリーダーがどんどん短くなってしまうのだ。このスタイルはいただけないな。
 プロップR KOOLABUNG LURES
プロップR KOOLABUNG LURES 
クーラーバングルアーズのブリーム、バス、サラトガなどをターゲットとしたポッパーで価格はA$10.25。プロペラは付いていないのに、何故この名前が付いているのかちょっと理解できない。特徴的なのはボデイの頭に取り付けられたカップ。このカップは運動グツのソールに使われる素材で作られている。そのおかげでポップ音は生物感のある音質となっている。
豪州にはこの手のスタイルのポッパーや、ボディその物が同素材で作られたルアーが数社から販売されている。ソフトタッチで魚の食い込みは良いのだろうが、欠点は使っている内に劣化し、ポロポロと崩れることだろう。
 ソフティー KOOLABUNG LURES
ソフティー KOOLABUNG LURES 
クーラーバングルアーズの軟質プラスチックボディで作られたルアー。ボデイは小さいのだが、ニュッと伸びた大きなリップが特徴。サイズは5cmで3m潜る。そして、このルアー最大の特徴は名前が示すとおり、指で摘むとフニャフニャしている事。金属プレートを軟質プラスチックで挟み込み、リップを突き刺しただけのシンプルな作り。ボデイの硬さが丁度魚っぽいので、一旦食いついたプレデター達は直ぐには吐き出さないハズ。
しかし、鋭い歯を持つ魚が多い豪州で、このルアーの寿命は短そうだ。昔、USAのバーク社が作っていたルアーと同類のコンセプトなのだが、こちらの方が遥かに釣れそうな雰囲気が漂っている。カラーはラメラメでハデハデなのでイイ感じ。価格はA$11.50。
 リオズ・プラウン Rio's Lures
リオズ・プラウン Rio's Lures 
す〜うっと伸びたヒゲや透けて見えるお腹の中の内臓もちゃんと作っており、一瞬本物かと思ってしまうほどの質感があるエビにそっくりなルアー。私のお勧めカラーは、エビっぽいラメ入りのゴールドフレークだ。10.5cm、19gで価格は A$11.99。製造メーカーはクイーンズランド州にある。オーストラリアのルアーは、パッケージがシンプルでルアーの名前と潜る深さが書いてあるだけの物が多いが、このルアーは折りたたんだ台紙の内側に使い方が書かれており良心的。ラインアイがアゴ下に付いている不思議なルアーなのだが、その秘密がこれを読むと判るのだ。
このルアーは他のエビ系ルアーと違い、ボトムや中層狙いの使い方だけでなく、表層でも使うことを考えてアゴ下にラインアイを付けている。フルキャストしてファストリトリーブをすると胸の部分で水を受けてルアーが浮上し、水面を逃げ惑うエビを演出できGTやクイーンフィッシュ狙いで使えるのだ。また、オーバーハング下やブッシュにおいてはボディ形状から着水後やトウィッチ後にバックスライドするため、更に奥深くルアーを送り込める。これで潜んでいるプレデターの鼻先にルアーをプレゼンテーション出来るのだ。使い方に幅があり実績も多いので、長い間、豪州人に愛されているのだろう。
オーストラリア遠征目次へ